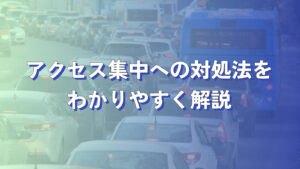アクセス集中の「お詫び」について解説。謝罪が必要なラインや例文も紹介
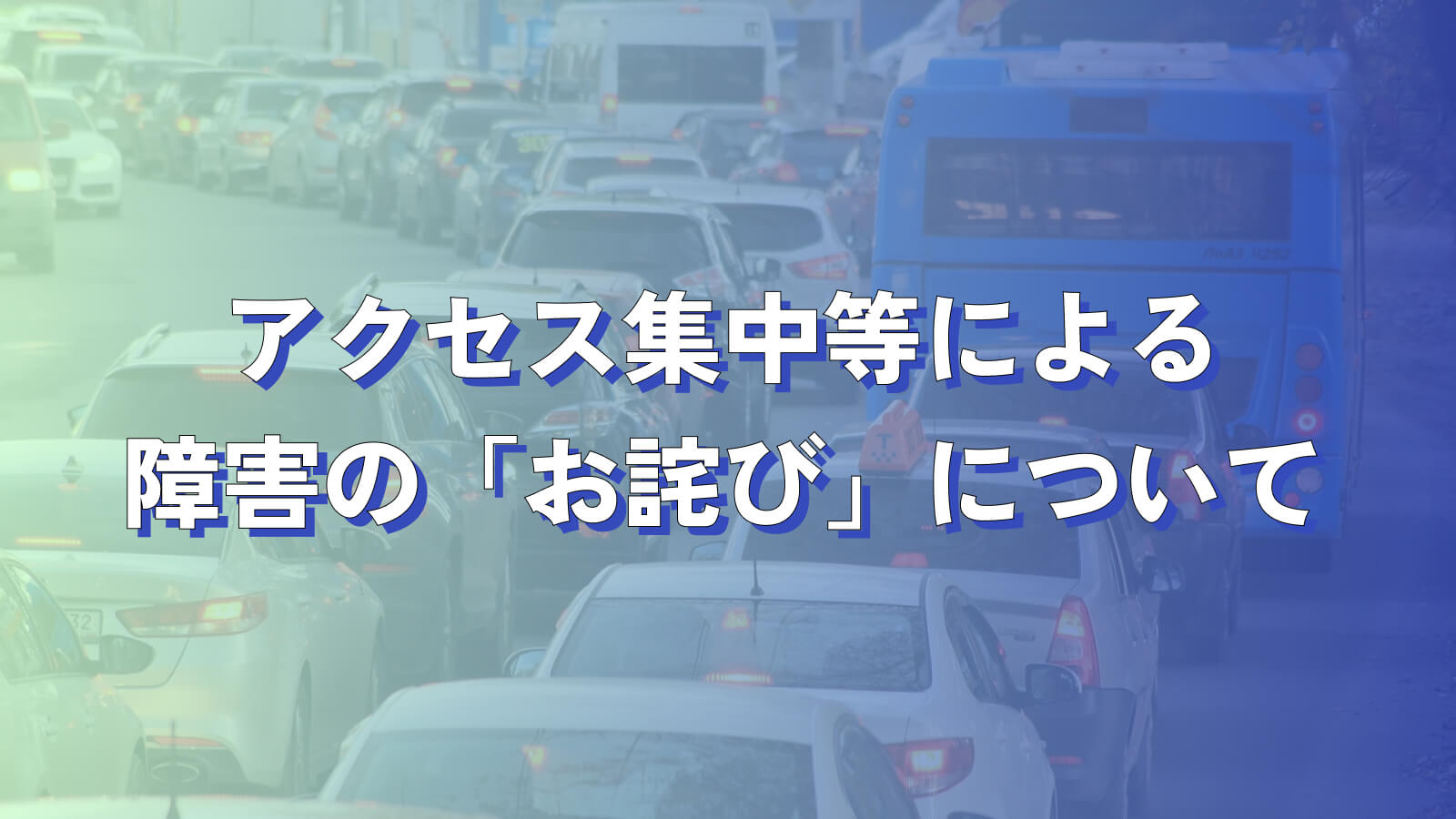
アクセス集中による障害が発生した際、頭を悩ませるのが「どこまでお詫びをすべきか」という判断です。
単に「謝罪すればいい」というものではなく、影響の度合いによっては不要な謝罪が逆効果になることもあります。過度なお詫びはユーザーの不安を煽る可能性があり、逆に対応が遅れるとクレームにつながることも。
この記事では、具体的なケースごとに「お詫びが必要なライン」と「お詫び不要なケース」を整理し、適切な対応をするためのポイントを解説していきます。
アクセス集中時、お詫びが必要なライン
アクセス集中などにより発生する障害には、ユーザーに直接的な影響を与えるものと、影響が限定的なものがあります。重要なのは、「どの程度の影響が出た場合に、どのような形で謝罪をするべきか」というラインを明確にしておくことです。
ここではお詫びの必要性を判断する目安として、具体的なケースごとにお詫びが必要なラインを整理します。
サービス運営者としては、どの程度ならお詫びすべきか判断が難しいですよね。「とりあえず謝ればいい」と考えることもできますが、肝心なときの謝罪効果が薄れたり、雑な対応だと非難されたりするリスクがあるので、そのラインを見極めておきたいところです。
回線混雑による遅延
アクセスが集中しすぎると、ウェブサイトやアプリの動作が遅くなり、ユーザーが快適に利用できなくなることがあります。特に、ビジネスシーンや予約システムでの遅延は、ユーザーにとって大きなストレスになるため、適切な対応が求められます。
▼お詫びが必要
- ページやアプリの読み込みが極端に遅く、通常より5秒以上の遅延が発生している場合
- ユーザーが操作中に頻繁に読み込み待機状態が発生する場合
- システム全体のレスポンスが著しく低下し、業務利用や予約などに支障をきたす場合
▼お詫び不要
- 一時的な軽微な遅延(数秒程度)であり、すぐに回復する場合
- 高負荷の発生が事前に予測され、ユーザーに事前告知している場合
サーバーダウン(サービスが完全に停止)
サーバーが完全に停止すると、ユーザーはサイトやアプリを全く利用できなくなります。特に、ECサイトや金融サービスなどでは、即座に対応しなければ大きな損害や信頼の低下につながる可能性があります。
▼お詫びが必要
- サーバーがダウンし、サービスが完全に停止している場合
- 復旧の目処が立たず、長時間(30分以上)影響が継続する場合
- アクセス過多により、ログインや注文など主要機能が一切利用できない場合
▼お詫び不要
- 数分以内に復旧し、影響が最小限で済んだ場合(ただし、事前告知があればベター)
データベースエラーによる一部機能の停止
データベースに負荷がかかると、特定の機能が使えなくなり、ユーザーが情報を取得できなくなることがあります。特に、決済やアカウント管理に関わる機能の停止は、早急な対応が必要です。
▼お詫びが必要
- 注文・決済関連の情報が正しく表示されない、または反映されない場合
- 会員情報の編集・閲覧ができない状態が続く場合
- サイトのコア機能(例:検索、在庫確認)が使えない場合
▼お詫び不要
- 一時的に特定の機能が遅延するが、影響範囲が限定的な場合
- サービスの主要機能には影響せず、短時間で回復する場合
ログイン障害
ユーザーがアカウントにアクセスできない状況は、利用の継続を妨げる重大な問題となります。特に、セキュリティ関連のトラブルが絡む場合は慎重な対応が求められます。
▼お詫びが必要
- 大多数のユーザーがログインできない状況が15分以上継続する場合
- ログイン情報が正しく入力されているにもかかわらず、エラーが出る場合
- セキュリティ関連の機能(二段階認証など)が機能せず、ログインできない場合
▼お詫び不要
- 一部の端末・ブラウザのみで発生し、代替手段がある場合
決済システムの不具合
決済に関わるトラブルは、金銭的な損害やユーザーの不信感につながりやすいため、特に慎重な対応が必要です。
▼お詫びが必要
- クレジットカードや電子決済が利用できない状態が続く場合
- 決済完了後に注文が反映されないなど、金銭に関わる重大な影響がある場合
- 二重決済や誤請求が発生した場合
▼お詫び不要
- 一部の決済方法でのみ発生し、ほかの決済手段が使える場合
予約・申し込みシステムの停止
予約ができないと、ユーザーが購入やサービス利用の機会を逃し、ビジネスの損失にも直結する可能性があります。
▼お詫びが必要
- 予約・申し込みができず、販売機会を逃すユーザーが多く発生する場合
- 申し込み後の確認メールが届かず、ユーザーが不安を抱える状況
▼お詫び不要
- 短時間(数分程度)の障害で、影響が限定的な場合
メール・通知システムの遅延
ユーザーにとって重要な通知が遅れると、アカウント管理や決済の確認ができず、不安を与えることがあります。
▼お詫びが必要
- 決済完了やアカウント認証など、重要な通知が遅延し、ユーザーの行動に支障が出る場合
▼お詫び不要
- プロモーションメールや一般的な通知の遅延(ただし、影響を受けるユーザーには事後報告が望ましい)
APIの応答遅延・外部サービスとの連携エラー
外部サービスとの接続が不安定になると、ログインや決済、在庫確認などの機能が正常に動作しない場合があります。
▼お詫びが必要
- 外部サービスの影響により、主要な機能(ログイン、決済、在庫確認)が使えない場合
▼お詫び不要
- 一部の機能でのみ発生し、影響が軽微な場合
アクセス集中による障害が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。ユーザーの信頼を損なわないためには、問題の把握から社内調整、ユーザーへの通知までの流れを明確にし、スムーズに対応できる体制を整えることが重要です。
アクセス集中時のお詫びまでの流れ
ユーザーの信頼を損なわないためには、問題の把握から社内調整、ユーザーへの通知までの流れを明確にし、スムーズに対応できる体制を整えることが重要です。
- 状況把握
- 初動対応
- 社内での情報共有
- 対応方針の決定
- ユーザーへの通知
1)状況把握
障害が発生した際、まずは「何が、どれくらいの影響を与えているのか」を正確に把握する必要があります。この段階で誤った判断をすると、対応が遅れたり、不適切な通知を発信したりするリスクがあるため、慎重かつ速やかに状況を確認することが重要です。
障害は、以下の3つの方法で検知されることが多いです。
| 検知方法 | 具体的な手段 | 備考 |
|---|---|---|
| 監視ツールのアラート | サーバーログ、負荷監視ツール(Datadog, New Relic, CloudWatchなど) | システム的に異常を自動検知 |
| 社内システムの異常ログ | エラーログ、データベース負荷、レスポンスタイムの急激な上昇 | 管理画面で確認 |
| ユーザーからの問い合わせ・SNS投稿 | カスタマーサポート、X(旧Twitter)やFacebookの投稿 | 実際の影響度を確認可能 |
障害の検知後は、障害の影響範囲を特定します。
- 影響を受けるユーザーの範囲(全ユーザー or 一部地域・端末のみ)
- 影響を受けている機能(ログイン・決済・表示遅延など)
- 発生している頻度と継続時間(断続的か、完全停止か)
- 影響があるページやシステム(特定のURLやAPI)
2)初動対応
状況を把握したら、障害の拡大を防ぐために即座に対応を開始します。
初動対応の目的は、「システムの安定化」と「影響の最小化」です。ここで適切な対策を講じることで、サービスの完全停止を防ぎ、復旧作業を円滑に進めることができます。
システムへの負荷を軽減
アクセス集中による障害では、まず負荷を軽減することで、システム全体がダウンするリスクを抑えます。
- キャッシュの強化
静的コンテンツ(画像、CSS、JavaScript)をキャッシュし、サーバーへのリクエスト数を減らす - CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の活用
トラフィックを分散し、特定のサーバーに負荷が集中するのを防ぐ - サーバーのスケールアップ
クラウド環境の場合、一時的にサーバーリソースを増強し、処理能力を向上させる
これらの対策を施すことで、アクセス増加によるパフォーマンス低下を防ぎ、システムの安定稼働を維持します。
一部機能の制限
すべての機能を稼働させ続けると、負荷が分散せず、復旧が遅れる可能性があります。そのため、優先度の高い機能を維持し、低い機能を制限することで、システム全体の安定性を確保します。
- 優先度の低い機能を一時停止
検索機能、ランキング更新、画像の高解像度表示など、即時に必要でない機能を停止 - APIリクエストの制限
外部サービスとのデータ連携を制限し、内部の処理負荷を下げる - ログイン制限の導入
ユーザーのアクセスを段階的に分散し、一度に大量のログインが発生するのを防ぐ
これにより、決済やログインなどの最も影響が大きい機能を優先的に維持できるようになります。
復旧作業の準備
負荷を抑えながら、復旧に向けた作業を進めます。
- エラーログとサーバーログの解析
どの処理で負荷が発生しているのかを特定し、ボトルネックを解消 - データベース負荷の最適化
クエリの処理負担を減らし、データベース接続エラーを防ぐ
この段階で、一時的な対応と長期的な改善の両面を考慮しながら、障害対応を進めます。
3)組織内での情報共有
障害の内容と影響範囲が明確になったら、速やかに組織内で情報を共有し、対応体制を整えます。
障害が発生した際に、組織内で共有すべき情報は以下のとおりです。
| 共有項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 障害の内容 | 何が発生しているのか(サーバーダウン、遅延、ログイン障害など) |
| 影響範囲 | どの機能・サービス・ユーザーが影響を受けているのか |
| 発生時間 | 障害の発生時刻と継続時間 |
| 原因の推測 | アクセス集中によるものか、その他の要因か |
| 対応策 | 即時対応可能なこと、復旧にかかる時間の見込み |
| ユーザーへの影響 | 利用制限の有無、業務影響の程度 |
- エンジニア
監視ツールを確認し、技術的な対応を開始 - カスタマーサポート
ユーザーからの問い合わせが増加している場合、社内アナウンスを確認 - 広報・マーケティング
SNSや公式サイトでの発信を準備 - 経営層・マネジメント
必要に応じて報告し、対応方針を決定
4)対応方針の決定
社内で情報を共有した後、次のステップとして対応方針を決定します。対応方針は、障害の規模や復旧見込みによって変わります。
短時間で復旧可能な場合(軽度の障害)
このレベルの障害は、一時的なアクセス集中によりサイトの動作が遅くなる、特定の機能だけが影響を受けるなど、比較的影響が小さいものです。サービス全体が完全に停止するわけではなく、適切な対応を行うことで短時間で復旧できる可能性が高い状況です。
対応策
負荷分散、キャッシュ利用、サーバー増強
お詫びの要否
短時間で復旧可能なら、軽微な遅延は告知不要
ただし、影響が大きい場合はSNSなどで軽く言及するのが望ましい
長時間の影響が見込まれる場合(中~重度の障害)
このレベルの障害は、復旧に時間がかかると予測されるものです。例えば、ログインができない、決済が完了しない、特定のページが完全に表示されないなど、ユーザーに大きな影響を与える場合が該当します。
対応策
障害復旧作業の開始と、復旧見込みの算出
お詫びの要否
公式サイトやSNS、メールなどでユーザーに状況を通知し、お詫びを伝える
影響が広範囲に及ぶ場合(重大な障害)
このレベルの障害は、システム全体が停止している、または多くのユーザーに深刻な影響を及ぼしている状況です。例えば、ECサイト全体がダウンし、すべてのユーザーがアクセスできない、または大規模なデータ損失が発生している場合などが該当します。
対応策
システム全体の点検、エンジニアの総動員、外部の支援も検討
お詫びの要否
即時に正式な謝罪文を発表し、ユーザーへの対応方針もセットで提示
5)ユーザーへの通知
アクセス集中時の障害についてユーザーへ適切に通知することで、不満や混乱を最小限に抑えることができます。
通知をする際は、以下のように基本原則を定めておくのが望ましいでしょう。
- 早期に通知する
状況が完全に把握できていなくても、影響がある場合は「調査中」の旨を伝える - 簡潔に説明する
専門用語を避け、ユーザーが理解しやすい言葉を使う - 復旧見込みを伝える
復旧時間の予測がつく場合は伝える(確定できない場合は「続報をお知らせします」と補足) - 対応策も伝える
一時的な回避策がある場合は提示する
また、サービスや影響範囲により、どのような手段で通知するのか検討する必要があります。
| 通知手段 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 公式サイト | 影響を受ける全ユーザーに一括通知が可能 | 公式サイト自体がダウンしている場合は他の手段が必要 |
| SNS(X、Facebookなど) | リアルタイムで情報を発信しやすい | 一部のユーザーにしか届かない可能性がある |
| プッシュ通知(アプリ) | アプリユーザーに直接通知できる | スマホの通知がオフになっていると届かない |
| メール | 重要な内容を正式に伝えられる | 長文になりすぎないように注意 |
| カスタマーサポート(FAQ更新) | 問い合わせが減る | 問い合わせが急増する前に更新することが重要 |
アクセス集中時に使えるお詫び文言・お詫びメールの例文
ここでは、公式サイト(プレスリリース)やSNSでの発信に適したお詫び文の例を紹介します。
| 構成要素 | 例 |
|---|---|
| 障害の発生報告 | 「現在、一部のユーザーにアクセスしづらい状況が発生しております。」 |
| 影響範囲 | 「ログインおよび決済に影響が出ており、サービスをご利用いただけない可能性があります。」 |
| 復旧見込み | 「現在、復旧作業を進めており、およそ◯時間以内に正常化する見込みです。」 |
| お詫び | 「ご不便をおかけして申し訳ございません。」 |
| 次回の情報提供 | 「新たな進捗があり次第、こちらのページ・SNSでお知らせいたします。」 |
この基本形さえ押さえておけば、例文をコピペせずとも正確な情報伝達ができるはずです。
公式サイト(プレスリリース)でのお詫び文例
公式サイト(プレスリリース)は、障害が発生した際に最も多くのユーザーが訪れる情報源です。影響を受けたすべてのユーザーに向けて、状況の詳細や対応方針を正確に伝えることが求められます。
軽度の障害
タイトル例:現在、一部のサービスにアクセスしづらい状況です
平素より【サービス名】をご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在、アクセス集中により、一部のサービスで表示の遅延が発生しております。
【影響範囲】
・ページの表示速度が遅くなる場合があります。
・検索機能の動作が不安定になる可能性があります。
【対応状況】
現在、負荷軽減のための対応を進めております。復旧の見込みは**○時頃**となっております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。復旧まで今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。
中~重度の障害
タイトル例:システム障害発生のお知らせとお詫び
【サービス名】をご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在、アクセス集中の影響により、以下のサービスが正常にご利用いただけない状況です。
【影響範囲】
・ログインができない
・決済手続きが完了しない
・予約申し込みが完了しない
【対応状況】
システム復旧に向け、現在エンジニアチームが対応を進めております。
現時点での復旧見込みは○時頃となります。進展があり次第、本ページおよび公式SNSにてお知らせいたします。【お問い合わせ】
お急ぎの方は、以下のサポート窓口までお問い合わせください。
・カスタマーサポート:[問い合わせページのURL]
・電話対応窓口:[電話番号](受付時間:9:00〜18:00)
ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
SNSでのお詫び文例
SNS(X(旧Twitter)・Facebook・Instagramなど)は、リアルタイムで状況を伝えるのに適したツールです。短文で簡潔に伝えつつ、公式サイトへの誘導を行うのがポイントです。
軽度の障害
X(旧Twitter)投稿例
【お知らせ】現在、アクセス集中により、ページの表示が遅くなる現象が発生しております。
復旧作業を進めておりますので、しばらく時間をおいて再度お試しください。
詳細は公式サイトをご確認ください▼
[URL]
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
中~重度の障害
X(旧Twitter)投稿例
【重要】現在、システム障害によりログインおよび決済機能がご利用いただけない状態です。
復旧作業を行っておりますが、完了まで○時頃を予定しております。
進捗は随時更新いたします。詳細はこちら▼
[URL]
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
復旧後の投稿例
X(旧Twitter)投稿例
【復旧のお知らせ】
アクセス集中によるシステム障害が解消し、通常どおりサービスをご利用いただけるようになりました。
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後とも【サービス名】をよろしくお願いいたします。
【事例】他社(他団体)のアクセス集中などによる障害のお詫び対応
障害発生時の対応事例として、総務省(地方税電子化協議会)、KADOKAWA、PR TIMESの3つのケースを紹介します。
アクセス集中によるもの以外もありますが、いずれも自社のシステム障害時の対応方針を策定する際の参考になるはずです。
総務省(地方税電子化協議会)の事例:eLTAX接続障害
発生時期:平成29年1月27日~2月1日
影響範囲:地方税ポータルシステム「eLTAX」で電子申告等が繋がりにくくなる
対応策:負荷上限の引き上げ、通信機器設定の変更
地方税ポータルシステム「eLTAX」において、1月27日から2月1日にかけてアクセス集中とシステム障害が発生し、電子申告が繋がりにくくなる問題が生じました。特に月末・月初の繁忙期と重なったため、多くの利用者に影響を与えました。
総務省のお詫び対応
- 公式発表として「システム障害が発生したことにより、利用者の皆様には大変なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。」と謝罪
- 再発防止策の明示として「今後、このようなシステム障害が生じないよう、再発防止に努めてまいります。」と公表
KADOKAWAの事例:大規模サイバー攻撃によるシステム障害
発生時期:2024年6月8日
影響範囲:「ニコニコ」関連サービス、出版事業、MD事業、経理業務
対応策:サーバーシャットダウン、復旧計画の公表、影響範囲の特定
2024年6月8日、KADOKAWAグループの複数のサーバーに対し、ランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃が発生。影響を受けたシステムには「ニコニコ」関連の動画サービスや出版業の受注システム、オンラインショップの運営管理などが含まれた。
KADOKAWAのお詫び対応
- 公式発表として「読者やユーザー、作家・クリエイター、取引先、株主・投資家をはじめ、関係するすべての皆様に、多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。」と謝罪
- 復旧見込みの提示として「6月末を目処として、基幹システムの復旧を目指します。」と公表
- ビデオメッセージの公開としてKADOKAWA代表取締役社長やニコニコ代表が直接説明
出典:【第2報】KADOKAWAグループにおけるシステム障害について
PR TIMESの事例:ネットワーク障害による接続障害
発生時期:2019年8月19日
影響範囲:PR TIMESサイトのアクセス不能、プレスリリース配信停止
対応策:ネットワーク機器の見直し、データセンター移行
2019年8月19日、ネットワーク機器の通信用回線異常により、PR TIMESサイトへのアクセスが不能となり、プレスリリースの配信機能も停止。約7時間にわたり、会員企業のリリース配信が遅延・未送信となった。
PR TIMESのお詫び対応
- 公式発表として「会員企業様、会員メディア様、ユーザーの皆様ならびに関係各所の方々へ、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。」と謝罪
- 補填の実施として「予約時間通りの配信が叶わなかった従量課金プランの会員企業様には、該当のプレスリリース配信41本を無料とさせていただきます。」と対応
出典:PR TIMES 接続障害および配信機能停止に関するお詫びと経緯報告(詳報)
お詫び後は、再発防止が不可欠
アクセス集中による障害が発生した際、迅速なお詫びと適切な対応が求められます。しかし、もっとも重要なのは「同じトラブルを繰り返さないこと」です。
サーバーダウンやアクセス遅延を防ぐためには、適切なインフラの見直しが不可欠です。特に、高負荷時の対応力を向上させるためのシステム強化が重要になります。
- レンタルサーバーからの移行
- CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の導入
- 運用保守の最適化
当社(サーバーダウン対策の窓口)では、これらの施策を低コストで実施できるソリューションをご提供しています。
一度の障害でユーザーの信頼を失わないためにも、再発防止策を講じ、安定したサービス提供を目指しましょう。